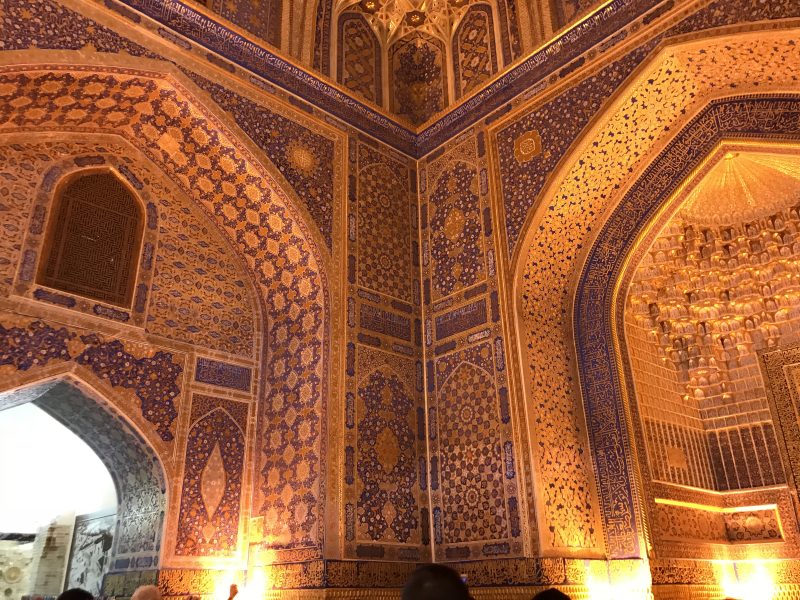- バックパックがおすすめの理由
- バックパック選びのポイント
- 私たちがキャビンゼロを選んだ理由
- キャビンゼロミリタリーとクラシック、どっちがおすすめ?

旅行に使うバックパックで迷っている人は、きっと参考にしていただけると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
バックパックがいい理由
さて、そもそも旅行の荷物はスーツケース派の人も多いと思います。足のコロコロがあることから、運搬はとても便利ですよね。

ですが、私たちはそのメリットを諦めてでもバックパックを推したい理由があります。それぞれを詳しく紹介しましょう。
空港からい ち早く脱出できる

各航空会社の規定サイズ内であれば、バックパックは持ち込み手荷物として飛行機内の座席上部の棚に持ち込み可能です。言い換えると、チェックインの際に預け入れしないですみます。
そのため、目的地の空港から脱出する際、荷物受け取りに待たされる必要がありません。
これはとても便利。長距離フライトで体力を奪われ、入国審査で時間がかかり、そのうえ荷物回収で待たされるとなると、観光前にもうヘトヘト。荷物を預け入れしなければ、少なくとも荷物回収で待たされるストレスからは解放されます。
ツアーの場合は、他の参加者さんの荷物をどのみち待つことになるので関係ないですが、個人手配の旅行の場合は、すぐに空港から脱出できるので、バックパックをおすすめします。
ロストバゲージの心配がない

また、機内持ち込み可能なバックパックであれば、預け入れないため荷物が行方不明になることがありません。いわゆるロストバゲージというもので、飛行機への荷物の積み込みミスや、経由地での便の間違いなどから荷物が紛失することがありますが、それが防げるのです。
ネットで調べたところ、ロストバゲージの確率は0.76%とのこと。この数字の信憑性は別としても、ざっくり100人に1人の割合で荷物が紛失している可能性があるなら、搭乗の際、都度荷物を預け入れる限り、遅かれ早かれ荷物はなくなってしまいそうです。
荷物を紛失したら、せっかくの旅行も楽しめませんよね。また、行方不明になった荷物は、最悪手元に戻ってこないケースもあるようです。であれば、最初からロストバゲージになるリスクを回避するべき!その観点からも機内持ち込み可能なバックパックをおすすめします。
石畳や坂道でもストレスがない

スーツケースのメリットの一つに、足のコロコロのおかげで背負わず引いて行ける点が挙げられます。ですが、それがデメリットになることも。
例えば、ヨーロッパだと石畳の道が多いエリアがありますが、その場合、コロコロと引いて運ぶのはとても難しいです。また、坂道や階段が多い場所も同じことが言えます。
その点、背負ってしまえばOKなバックパックは、機動力が優れています。
バックパック選びのポイント

さて、続いてバックパック選びのポイントについて紹介したいと思います。
機内持ち込み可能なサイズかどうか?

まず、ここまで紹介した通り、バックパックの強みは機内持ち込みできることにあるわけですが、実はこれ、どんなバックパックでも持ち込めるわけではないのです。
具体的にいうと、各航空会社は機内へ持ち込める荷物のサイズに規定(きてい)を設けて(もうけて)いるため、そのサイズ内でないといけません。
なるべく軽いバックパックであること

また、各航空会社はサイズだけでなく重量にも規定を設けています。身の回り品を除いて7キロまで、言い換えると、バックパックだけで7キロまでというのが一般的です。
そこで重要なのがバックパックの重さ。バックパック含め7キロ以内にしないといけないため、それ自体が軽ければ荷物を増やせます。逆に、バックパックが重たいと荷物を減らす羽目になりますので、なるべく軽いバックパックを選びましょう。
容量で選ぶ

バックパックを探していると、44Lや36Lなどの数字を見ると思います。これ、何を指しているかというと、荷物を詰め込める容量をリットル表記しています。
50リットルを超える登山用バックパックもあれば、普段使いにも使える20リットル前後のカジュアルなものまで。バックパック選びに大切なのは、ご自身がどのようなスタイルなのかということ。
1泊・2泊の短期旅行が多く、更に毎日の通勤通学でも使いたい人は、小さめのバックパックが良いですが、それだと1週間の旅行はかなり難しいです。
対して、50リットルを超えるようなバックパックだと、サイズ的に飛行機の機内持ち込みがパスできないため、肝心の旅行には不向き。ですが、登山がメインで飛行機を使った旅行の頻度が少ない人は、預け入れ荷物にする前提で、ありだと思います。
このように、どのような旅行や使い方をするかで、バックパックの容量を選ぶと良いでしょう。
オプション機能で選ぶ

バックパックにはそれぞれ特徴的な機能があったりします。
例えば、レインカバーが付属しているタイプや、メインの収納スペースに鍵がかけられるタイプ、バックパックのサイドにドリンクホルダーがついているタイプに、チェストベルトやウェストベルトがついているタイプなど様々なオプション機能があります。
ご自身の使い方で必須の機能があれば、その有無で選ぶのも良いでしょう。
キャビンゼロミリタリーを選んだ理由

と、ここまででスーツケースよりバックパックが良い理由や、その選び方について紹介したわけですが、私たちは冒頭でもお伝えした通り、こちらのキャビンゼロをメインのバックパックとして使っています。
では、なぜキャビンゼロを選んだのか?ですが、端的にいうと、
- 44リットルのサイズでも機内持ち込みが可能
- 機能性に優れている
と感じたからです。

実は、最初に購入したのはミリタリー。こちらは、機内持ち込みサイズだったことに加え、通常のナイロン素材よりも厚い1000デニールの防刃性ナイロンで作られていることや、小物を引っ掛けるのに便利な帯が複数あること、そして、背負った際に密着させることで負担を少なくするチェストベルトとウエストベルトがある点などが気になって購入しました。

結果、飛行機の機内持ち込みに関しては、春秋航空・中国国際航空・タイ国際航空などの一般的な航空会社はもちろん、香港エクスプレスやタイガーエア、ブエリング航空といったLCCでも問題なく持ち込めました。
対して、実際に使ってみての機能性の部分ですが、幸いなことに防刃性であることで恩恵は受けたことはまだなく、小物を引っ掛ける帯は一度も使わず、体を密着させるチェストベルトは便利なものの、ウエストベルトは使わない際はいちいち折り畳まないとぶらんとしてしまい、歩いていると手に当たったり、飛行機の座席上部の物置に入れる際、他の人の荷物に引っかかりそうで使わなくなってしまいました。
これは全て夫の話。ただ、物自体は大満足とのことだったので、わたし用に買い足したのは、あまり恩恵を受けていないこれら機能を削ぎ落とした、こちらのクラシックとなったわけです。
キャビンゼロクラシックが優れている点
結論、私自身はミリタリーではなくクラシックにして良かったなと感じています。
その1番の理由は、その軽さ。入れられる容量は44リットルとミリタリーと全く同じものの、重量には300グラムほどの違いがあります。

先ほども紹介した通り、飛行機の機内持ち込みは7キロ上限が一般的。そのため、バックパック自体の重量が300グラム軽くなるのは、とても大きな恩恵があります。例えば、予備として薄手のTシャツと下着を追加できますし、大容量のモバイルバッテリーを追加しても良いでしょう。
また、クラシックにはチェストベルトがないものの、飛行機のことも考えると結局詰め込むのは7キロまでとなるため、この程度であればチェストベルトがなくても苦もなく持ち歩けます。
お値段もミリタリーに対して安くなりますし、カラーのバリエーションも豊富。
過酷な環境で使いまくること前提ならミリタリーの方が良いと思いますが、そうではなく一般的な旅行であれば、クラシックで十分だと思いました。
ミリタリーとクラシックが共通して優れている点
ミリタリーとクラシックの共通した良い点も紹介したいと思います。
一つ目は、全開で荷物を入れられる構造になっていること。両サイドのベルトを外すと、ファスナーを大きく開けられます。そのため、荷物を入れる際もスーツケースと同じ様にザクザク入れられます。

これが上部しか開けられない物だと、荷物の出し入れがとても大変。クラシックゼロは、その煩わしさがないので助かっています。

また、ミリタリーもクラシックも、メイン収納のファスナーにはこの様な輪っかが空いているので、ここに鍵を通せばロックできます。私たちは普段からバッグのこのスペースにノートPCやタブレットを入れて海外へ行っているため、鍵がかけられるのはとても重要。その点でもキャビンゼロはとても助かっています。

背負いやすさもポイント。ミリタリー・クラシックともにショルダーストラップに横幅があるため、肩への負担が分散されます。ちなみに比べてみるとショルダーストラップも背面もミリタリーの方がクッションがありますが、正直7キロほどの重量であれば、そこまで大きな差は感じられませんでした。
ここまでの総括
今回は、旅行にバックパックをおすすめする理由から、選び方のポイント、そして私たちが愛用している「キャビンゼロ」のミリタリーとクラシックの比較までをご紹介しました。
スーツケースと比べ、機動力やロストバゲージなどのトラブル回避の面で優れているバックパックは、特に個人手配の旅行にぴったり。
中でも、キャビンゼロは機内持ち込みサイズでもしっかり容量が確保できる点が魅力です。
旅行スタイルに合わせてミリタリーとクラシックから選べるのも魅力ですが、そこまで過酷な旅を想定していないのであれば、コストパフォーマンス的にもクラシックの方が満足できると思います。